「web-magazine GYAN GYAN」では、第三者的な視点でロックを検証してきましたが、当サイトではプライベートな感覚で、より身近にロックを語ってみたいと思います。
★ カレンダー
| 09 | 2025/10 | 11 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
★ フリーエリア
★ 最新コメント
[01/25 matsuZACK]
[01/23 shiba]
[01/02 matsuZACK ]
[01/02 ういん]
[12/27 shiba]
★ 最新トラックバック
★ プロフィール
HN:
matsuZACK
年齢:
63
性別:
男性
誕生日:
1962/02/15
自己紹介:
matsuZACKです。
“下天のうちをくらぶれば~”の年齢に到達してしまいました。
ミュージシャンを目指したり、
音楽評論家や文筆業を目指したり、
いろいろと人生の奔流に抵抗してきましたが、
どうやらなすがままに、
フツーの人におさまりつつあります。
“下天のうちをくらぶれば~”の年齢に到達してしまいました。
ミュージシャンを目指したり、
音楽評論家や文筆業を目指したり、
いろいろと人生の奔流に抵抗してきましたが、
どうやらなすがままに、
フツーの人におさまりつつあります。
★ ブログ内検索
★ 最古記事
★ P R
★ カウンター
★2009/09/20 (Sun)
さて、
例のごとく一気に納品された、
ドゥービー・ブラザースとフラワー・トラヴェリン・バンド…。
(以下、名前が長いのでドゥービー、FTBと略します)
どう考えても接点がないというか、
まったく正反対のサウンドと思われたのですが、
じつは意外な共通点に気がつきました。
それは両者共に、
たっぷり、
サイケデリック・ロックの洗礼を受けているという点です。
名曲「リッスン・トゥ・ザ・ミュージック」が収録されている、
ドゥービーの『トゥルーズ・ストリート』は1972年の発表。
一方、FTBの問題作『SATORI』は1971年の発表。
ともにバンドのセカンドアルバム。
両者はほぼ同時期に活動していたと言ってもよいでしょう。
とは言うものの、
このサウンドの違いは何でしょう?
スコーンと抜けたカリフォルニアの青空のようなドゥービーに対して、
もう、一音で終わっているというか、
救いようのない、果てしなく内面に落ちていくようなFTBの音。
私は別の場所で、
サイケデリック・ロックはイギリスに渡って、
プログレッシヴ・ロックに発展したと言いましたが、
さて、
本国アメリカや日本ではどうなったのか?
ということです。
サイケデリック・ロックは、
その背景に東洋思想が存在していたりしたものですから、
日本では特別な解釈が施されたようです。
つまり、
西洋ではインドへ行くところですが、
日本ではその前に、
自国の文化へ当てはめてみたということです。
結果的には、
歌舞伎、能、雅楽、仏教思想…、
このへんと相性がよかったらしく、
結果的に独自の発展を遂げていきました。
私が最近おもしろいと思い好んで聴いているのは、
このあたりの、
1970年代前半の日本の作品であり、
その独自性には、
いまさらながら目をみはるものがあります。
FTBはアレンジだけでなく、
リズム面でも、
日本文化特有の“間”を生かしたアプローチをしており、
その取り組みの深さには、
アタマが下がる思いがします。
欧米人がFTBを聴いたときには、
我々がユーロロックに興味を持ったときと同じように、
「日本人がロックをやるとこうなるんだろうなぁ」という、
予想通りの音に出会い、
きっと満足することでしょう。
それほど、日本文化の匂いが充満した作品。
どうも日本では、
イギリス同様、
サイケデリック・ロックを深く考え、
しっかりした解釈を与えたようですね。
しかし、
当のアメリカでは、
ドラックが簡単に手に入ることもあってか、
どうもその…、
「ラリって気持ちいい〜」の域から出られず…、
一過性の享楽的なムーブメントに終わり、
音楽的な発展は見なかったようです。
ドゥービーも、
バンド名にドラックカルチャーの痕跡をとどめるものの、
サウンド的にはとくにサイケデリック・ロックからの影響は感じられず、
その後は順調にアメリカンロックの王道路線を確立します。
ドゥービーとFTBのサウンドの違いこそ、
その後の両国におけるロックの発展を示唆している、
そう言ってしまったら、
言い過ぎでしょうか?
まぁ…そんなことを考えながら、
両者を聴いている今日この頃ですが…、
それにしても、FTBはスゴいなぁ〜。
石間さんのセンスって、
フツーじゃないですよ。
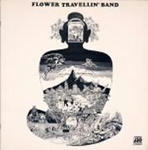
例のごとく一気に納品された、
ドゥービー・ブラザースとフラワー・トラヴェリン・バンド…。
(以下、名前が長いのでドゥービー、FTBと略します)
どう考えても接点がないというか、
まったく正反対のサウンドと思われたのですが、
じつは意外な共通点に気がつきました。
それは両者共に、
たっぷり、
サイケデリック・ロックの洗礼を受けているという点です。
名曲「リッスン・トゥ・ザ・ミュージック」が収録されている、
ドゥービーの『トゥルーズ・ストリート』は1972年の発表。
一方、FTBの問題作『SATORI』は1971年の発表。
ともにバンドのセカンドアルバム。
両者はほぼ同時期に活動していたと言ってもよいでしょう。
とは言うものの、
このサウンドの違いは何でしょう?
スコーンと抜けたカリフォルニアの青空のようなドゥービーに対して、
もう、一音で終わっているというか、
救いようのない、果てしなく内面に落ちていくようなFTBの音。
私は別の場所で、
サイケデリック・ロックはイギリスに渡って、
プログレッシヴ・ロックに発展したと言いましたが、
さて、
本国アメリカや日本ではどうなったのか?
ということです。
サイケデリック・ロックは、
その背景に東洋思想が存在していたりしたものですから、
日本では特別な解釈が施されたようです。
つまり、
西洋ではインドへ行くところですが、
日本ではその前に、
自国の文化へ当てはめてみたということです。
結果的には、
歌舞伎、能、雅楽、仏教思想…、
このへんと相性がよかったらしく、
結果的に独自の発展を遂げていきました。
私が最近おもしろいと思い好んで聴いているのは、
このあたりの、
1970年代前半の日本の作品であり、
その独自性には、
いまさらながら目をみはるものがあります。
FTBはアレンジだけでなく、
リズム面でも、
日本文化特有の“間”を生かしたアプローチをしており、
その取り組みの深さには、
アタマが下がる思いがします。
欧米人がFTBを聴いたときには、
我々がユーロロックに興味を持ったときと同じように、
「日本人がロックをやるとこうなるんだろうなぁ」という、
予想通りの音に出会い、
きっと満足することでしょう。
それほど、日本文化の匂いが充満した作品。
どうも日本では、
イギリス同様、
サイケデリック・ロックを深く考え、
しっかりした解釈を与えたようですね。
しかし、
当のアメリカでは、
ドラックが簡単に手に入ることもあってか、
どうもその…、
「ラリって気持ちいい〜」の域から出られず…、
一過性の享楽的なムーブメントに終わり、
音楽的な発展は見なかったようです。
ドゥービーも、
バンド名にドラックカルチャーの痕跡をとどめるものの、
サウンド的にはとくにサイケデリック・ロックからの影響は感じられず、
その後は順調にアメリカンロックの王道路線を確立します。
ドゥービーとFTBのサウンドの違いこそ、
その後の両国におけるロックの発展を示唆している、
そう言ってしまったら、
言い過ぎでしょうか?
まぁ…そんなことを考えながら、
両者を聴いている今日この頃ですが…、
それにしても、FTBはスゴいなぁ〜。
石間さんのセンスって、
フツーじゃないですよ。
PR
